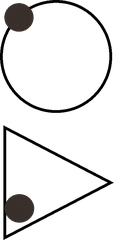『東京の色100』081~085
081 もんじゃ焼き
もんじゃを焼くとき、変化する生地の色は焼き具合を知るためのサインになる。
具材の土手に流し込まれたばかりの生地の色は、10YR7/4とベージュに近い色である。それが火が通るにつれて色相は赤みに寄り、明度と彩度が落ちていく。 火が通ったばかりの生地の色は7.5YR6/4であり、生地と具材を混ぜて食べごろになると、5YR6/3になる。さらにツウが知るせんべい(生地を横にずらすと鉄板に残る、薄い生地)の焼き色は、5YR4/4である。変化する色合いを見ながら焼き上がりを待つのも、もんじゃならではの楽しみである。
今回は、浅草にあるもんじゃ焼きの老舗、「ひょうたん」を訪れた。頼んだのは、駄菓子屋で食べた記憶のある方も多いであろう、キャベツとベビースターのもんじゃ焼きである。(昔はベビースターよりも、ラメックが一般的だったそうだが。)醤油のやさしい味付けが、次のもんじゃ焼きへの食欲をそそる。


もんじゃ焼きの起源は、江戸時代のおやつである「文字焼き」だという。子どもが鉄板に生地で文字を書き、覚えながら食べていたそうで、「文字焼き」という名前が変化して、「もんじゃ焼き」となった。
現在のもんじゃ焼きの形がほぼ出来上がったのは明治時代で、お好み焼きよりも歴史が長いという。その後もんじゃ焼きは下町に広がり、駄菓子屋で親しまれるようになった。
元は醤油で味付けしていたが、のちにウスターソースも使われるようになるなど、味や具材は地域や作る人で微妙に変わるそうだ。調味料や具材が異なれば、色も微妙に変わるだろう。
みなさんの記憶に残るもんじゃ焼きは、どんな色だろうか。
カラープランニングセンター 池田麻美

●マンセル値:5YR 6/3
●NOCS:5YR-2.6-7.0
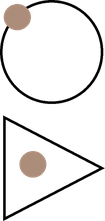
082 国立代々木競技場
2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、新国立競技場の建設は急ピッチで進んでいる。オリンピック開催国は国の威信を掛けて、競技場を建設してきた。北京のオリンピックスタジアム「鳥の巣」やブラジルのマラカナンスタジアムも記憶に新しい。1964年、東京オリンピックのメイン会場となった国立競技場も日本人の記憶の中に深く刻まれ

ているだろうが、建築物としては国立競技場よりも国立代々木競技場の方が世界的にも有名だろう。設計は丹下健三。吊り橋をつくるための吊り構造を応用して、優美な曲面の大屋根を持つ大空間をつくり出した。この国立代々木競技場はバスケットボールの競技会場として使われた第二体育館と共に、開会式が行われブルーインパルスが上空に五輪のマークを描いた国立競技場以上に世界の人に記憶される有名な建築物となった。
国立代々木競技場はコンクリートと金属の屋根で造られており、色彩は無彩色に近く、その分それまでの建築物には無かった吊り構造がつくり出すダイナミックなシルエットが印象的である。外壁のコンクリート打ち放しのマンセル値は、現在は少し汚れていて5Y 7/0.7あたりだろうか。多分建設当初はもう少し明度も高かっただろう。現在は改修中で2019年秋には再びきれいな姿に戻ることだろう。
この代々木競技場は吊り構造の優美な造形は多くの人の心を捉えたが、1964年の東京オリンピックで、私の中に印象的に残っている色彩は、亀倉雄策がデザインしたポスターである。日の丸を思わせる真っ赤な円と、金色の五輪マークを簡潔にデザインしたポスターは、まだデザインを知らなかった私にも鮮烈で誇らしい印象を与えた。
色彩計画家/クリマ代表 吉田愼悟

●マンセル値:5Y 7/0.7
●NOCS:5Y-0.75-5.8

083 皇居の夏の濃緑
東京都で千代田区千代田1番1号といえば、皇居のことだとわかる方も多いでしょう。ちなみに郵便番号は“100-0001”。周囲を取り巻く約5kmといわれる歩道は、都民のジョギングコースとして親しまれていますし、最近では多くの海外からの観光客が二重橋前の広場に訪れてもいます。
写真にあるように、夏の濃い緑に囲まれた皇居は、その正面に位置する近代的なビル群とはまさに正対するかのような存在として私たちの眼を癒してくれます。これら皇居の豊かに繁茂もする植生は、江戸城以降の貴重な生態系として永く守

られて、今日に至りました。
ディズニーアニメの傑作に『眠れる森の美女(1959)』があります。このアニメは、絵画のように美しい背景画とアニメーターによる最後の手仕事の作品であり、私にとっては最高のアニメ作品の一つとして記憶に残っています。
この『眠りの森の美女』において、茨の黒い森にびっしりと覆われて100年の眠りについているお城の姿が描かれます。このように、ヨーロッパの童話では、森は人々に敵対する存在としての性格を持っています。
それに比べて、皇居の緑、それも真夏の日差しの下で暗い影を纏う木々の深い緑は、コンクリートの近代ビル群に囲まれながら、貴重な自然の生命を育み、安らぎの眠りをもたらす聖なる森のように感じられます。
日本ファッション協会 山内 誠

●マンセル値 :5GY 4/4
●NOCS :5GY-4.4-10.8
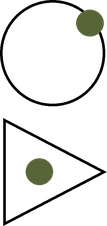
084 盛り場の赤ちょうちん
居酒屋の成り立ちには詳しくありませんが、ポンペイの遺跡にも酒場(ワインバー?)があったはずですので、人がいてお酒があれば、酒場ができるのは自然の成り行きなのでしょう。ただ、バーの文化が確立している欧米の人々にとっては、「食事」と「お酒」がこれほど一体化している日本の酒場という業態は、そうとう珍しい存在のようです。
日本人は一般に、「居酒屋」イコール「赤ちょうちん」と受け止めますが、この“赤ちょうちん”のスタイルは江戸時代に形成されたと言われます。それまでのお酒は、どうやら特権

階級に独占されていたようですが、江戸期になってようやく庶民が利用する酒場文化が発展、定着します。そんな中で出現したのが、江戸下町の赤ちょうちんだとか。この“夜間営業の目印にと、赤いちょうちんを吊ったお店が大繁盛”ということで、その後、居酒屋と赤ちょうちんが同義語になっていったようです。
そのおかげか、日本のサラリーマン(ウーマンも!?)は、誘蛾灯に群がる虫のように、やすやすと“赤”ちょうちんに誘われる存在になってしまいました。
赤い光は、刺激色として、食欲を増進させたり、行動を活発化するといわれますが、私の経験から言えば、酔った人間を呼び寄せる強い心理効果があるように思えてなりません。
日本ファッション協会 山内 誠

●マンセル値 :7.5R 4/12
(イメージ)
●NOCS :7.5R-7.4-6.2
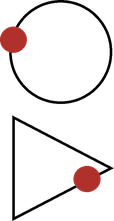
085 今半本店のすき焼き
「その輝きをおびたなまの食材は、やがて少しずつ大なべに移され、あなたの目の前で焼かれ、そこでおのおのの色と形と非連続を失い、やわらかくなり、本来の自然をなくし、醤油特有の色、焦げ茶色となる」
ロラン・バルトは、すき焼きを挙げてこう言っている。(ドミナント醤油!)
そこで、割下の色を測ってみると、5YR2/1。肉に葱に豆腐に白滝、麩が割下に染まった色を測ってみても、やはりYR系(黄赤)。見事に割下の色に染まっている。肉を噛むと、ぐっと甘みが染み出してくる…。この少し甘めの割り下の作り方は、社長と次期社長しか知らない。

すき焼きの調理の仕方は様々。神奈川の方で、割下の量が多く深いものは牛鍋と言うとか。柳田國男が鍋料理を「僅々五六十年の発明」(明治初期頃から)といい、仮名垣魯文が『安愚楽鍋』で「士農工商老若男女。賢愚貧福おしなべて。牛鍋食わぬは開花不進奴(ひらけぬやつ)」と書いているように、日本人が鍋料理を食べるようになったのも、牛肉を食べるようになったのも、文明開化の折からで、歴史は意外に新しいらしい。
東京下町の雰囲気が色濃く残る浅草で、親しい人と美味しいすき焼き囲んで食べつつ、風情に浸るのも楽しそう。
大沢光太郎建築塗装㈱ 大澤裕美
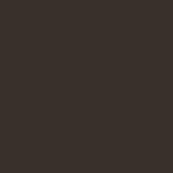
●マンセル値:5YR 2/1
●NOCS:5YR-0.9-15.8